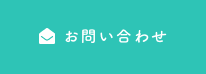News&Topics
スパイシーかき氷⁉
2024-07-24
NEW
かき氷のシロップと言えば、イチゴやメロン、練乳といったイメージですが、最近はインド風、メキシコ風などのエスニック・スパイシーなかき氷が流行りなんですね。
夏祭り、花火、イチゴシロップのかき氷といった定番の日本的情景を思い浮かべるのは、もう昭和世代だけなんでしょうかね。
同じ日のニュースが…
2024-06-27
6月26日の日経新聞朝刊。
”パートらの厚生年金加入 企業規模要件を撤廃”
”最低賃金「50円上げ」議論”
中小零細企業にとっては、固定費増につながる頭の痛い問題かもしれません。
ただ、社会保険の加入要件についても最低賃金の急激な上昇も、どちらも予測できていたことといえば予測できていたこと。
所与のものとして対処していかなくてはいけませんね。
やまなみ工房に見学に行ってきました!
2024-06-19
滋賀県甲賀市にあるやまなみ工房さま(http://a-yamanami.jp/)に見学に行ってきました。
利用されている皆さんが思い思いに創作活動をされています。描きたいものを描く、つくりたいものをつくる、ただそれだけ。それを他人は「アート」と呼んでるだけで、当の本人たちにとっては「アート」でもなんでもない、ただの日常。
これまで「アート」って難解だと思ってましたが、これこそが「アート」の本質なんじゃないかと感じました。実際、作品を前にするとグッと迫ってくるものもありましたしね。グランマ・モーゼスの展覧会で感じた気がした感覚の答えが見つかったような気がしました。
いろいろとお話しくださった施設長の山下完和さま、ありがとうございました!
さらにセミナーのお知らせ
2024-06-13
このところセミナーのお知らせが続いていますが、それだけ処遇改善に関する関心が高いということでしょうか。
今度は、東大阪で処遇改善についてお話しさせていただきます。
お申し込みはこちら。
お申し込みはこちら。
しかも今回は、記録請求ソフト”ほのぼの”でおなじみのNDソフトウェア様から報酬改定全般についてもお話しいただけます。
主催は、リコージャパン様(https://www.ricoh.co.jp/)。ご関心をお持ちの方はぜひご参加ください。
セミナーのお知らせ
2024-06-05
6/20(木)14時より、全国メディケア事業協議会様(https://www.issha-zenjikyo.jp/index.php)主催のセミナーが開催されます。デクノ社会保険労務士事務の相河が登壇するのは14時45分から。
タイトルは、「令和6年と令和7年の処遇改善加算の施設の対応」。
新しくなった処遇改善加算のポイントや処遇改善支援補助金も含めた実績報告書の書き方等々、わかりやすく解説します。
実績報告書作成に不安を感じている方、来年度までに何をすればいいのかわからないという方、ぜひご参加ください。参加無料です!